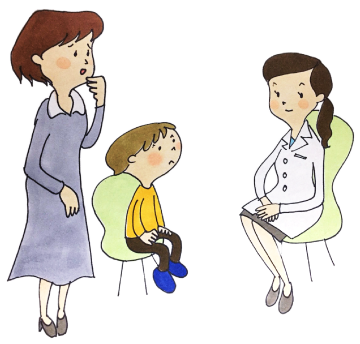コラム
COLUMNちょっとした知識や情報をお伝えするコンテンツ
サポチル20周年記念インタビュー 鈴木誠(監事)「『幸せに生きてもいいんだよ』を見つけるために必要な場所」[前編]
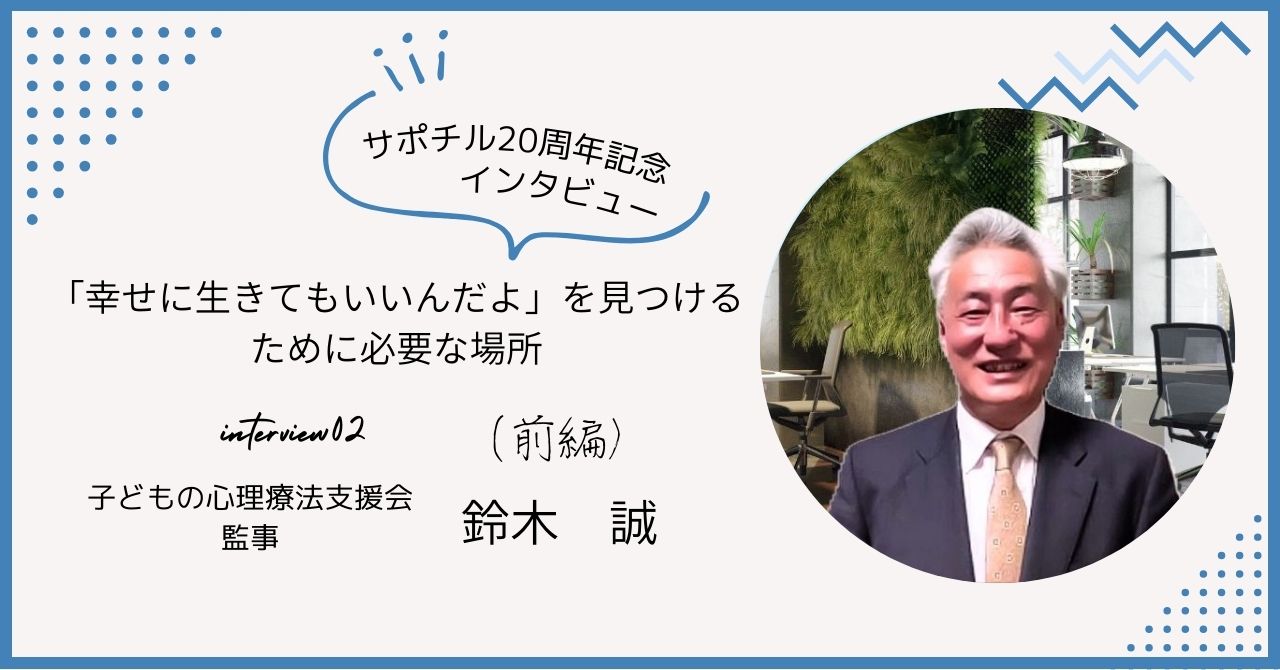
今回お話を伺ったのは、認定NPO法人「子どもの心理療法支援会」(サポチル)の監事を務める鈴木誠さん。
臨床心理士の資格を持ち、三重県にある「くわな心理相談室」では、大人の心理相談のほか、企業や組織へのコンサルテーションを行っています。現在は「日本ワークディスカッション研究会」の理事長としてもご活躍されています。
自身の臨床経験において、支援を必要としているのに費用の関係でそれがか叶わない人たちへ支援を届けたいという葛藤を覚えていたなか、国民が無料で医療を受けられる英国の取り組みをNPOレベルで挑戦するというサポチルの理念へ強い共感を覚え、創設期から活動へ携わってきました。
喪失の痛みは身近で繰り返されている
ーコロナ禍を経てコミュニケーション自体が大きく変容してきた時代のなかで、心理職の業界もまた、過渡期にあると考えます。鈴木さんから見て、現在の心理療法という分野において課題や傾向というものはありますか?
鈴木 サポチルが設立されたのは2005年になりますが、当時は児童虐待を受け施設に住んでいる子どもたちに対する心理療法的な支援はほとんどなかったと思います。それから20年経った今、各施設には心理療法士が配置されるようになったり、スクールカウンセラーが全国の小中学校に配置されるようになったり、かなり社会的なリソースが増えてきている現状はあると思います。
ただ、数は増えてきていますが虐待を受けた子どもたちが実際どこまでその心理療法にアクセスできるかと考えてみたときに、心理療法士の数が増えたほど増えていないのではないかというふうに感じています。
ケースワークやケースマネージメントはもちろん重要であり力点が置かれるべき部分ですが、長期にわたって傷ついた子どもたちの心をケアする心理療法にフォーカスが当たっていないというのが現代社会の問題だろうというふうに思っています。
私は学校に心の専門家を配置するというスクールカウンセラーの導入に試行段階から関わっていますが、その時にある種の期待がありました。学校というのはまだ救われていない、被虐待児やDVを目撃し続けている子どもたちへ直接身近に接する機会があるので、スクールカウンセラー制度がもっともっと発達していけば、そういう人たちにサイコセラピーを届けられるようになるのではないかと。
ただ、現状でのスクールカウンセラーの勤務は非常勤で週数時間。支援できる人たちは非常に限られているわけですし、個人のために定期的な時間の枠を確約するサイコセラピーばかり提供していると行政からはもっと平等に数多くの人たちに専門性を発揮して貢献するよう求められる。
経済的に困窮した家族や子どもが誰にも訴えることができないけど、スクールカウンセラーなどの身近な援助者にサイコセラピーを受けるという体制がここ20年以上経っても制度としてうまく機能していない状況には少し失望していますね。
スクールカウンセラーというのは年度雇用ですから、次の年そこにいられるかどうかわからない。あるいは、すべてのカウンセリングやサイコセラピーの援助は年度末で一旦区切るようにという指示が組織の中へ発せられることもあります。そうすると寸断された関係性の中をクライアントは生きなきゃいけない。それはなんというか、剥奪を再体験するような体験になっている可能性はあると思います。
支援者が守られていない、そんな不安定の中で…あるいは限定された期間の中でしか支援ができない。それは特に虐待のような、深い傷を負った子どもたちには手が届かない支援になってしまいますよね。
ー心理療法の現場で起きていることには、虐待やトラウマについて一般的な認識が広がっていないことが関係しているように感じます。
鈴木 一つは虐待トラウマという特殊なトラウマは、多くの人たちが目を背けたくなるほど悲惨であり直視できないということが背景にはあるというふうに思います。
虐待によって子どもが亡くなったり大怪我をして一瞬フォーカスが当たると新聞記事やニュースにはなりますけど、その後その子どもたちがどうなったかというフォローアップの報道ってほぼほぼなくって。事件性はあるけど、すぐ目を背けたくなる、それぐらい虐待を受けた子どもたちの心のトラウマは根深く悲惨だということなのだと思います。
ただ、見たくないものはできるだけ見ないように生きるっていうのはある意味健康さではあるのかもしれません。
例えば、児童養護施設で勤めているワーカーたちに、『貴方がケアしている子どもたちはこんな傷を負って、こんな痛みを持ちながら必死になって生きてるんですよ』と提示したときに、そんなことはわかってると思われるでしょう。確かに毎日接している子どもたちの心のみを考えてたら世話ができない、ケアができない。むしろそのことは忘れて、「私たちが必死になって関われば、この子たちは癒されていったり、将来真っ当に生きていけるかもしれない」と信じて身を粉にしてやるしかないんだみたいなところはあると思うんですよ。
それはメスを持って手術をする外科医が患者の痛みをアリアリと感じてしまったら患者の腹を開いて手術をすることができないように。考えないようにすることでその仕事がうまくできるということも一方ではあろうかと思います。
しかし多くの場合は、一度痛みを感じない、辛いものは見ないという風に考えてしまうとずっとそのままで切り替えられなくなってしまうんです。
―学校臨床においては試行段階から関わられていたということで、鈴木さんの経験の深さを改めて理解できたような気がします。そんな中で、そもそも鈴木さんがサポチルという組織に関わるようになったきっかけや動機などはどういったものがあったのでしょうか。
鈴木 私がサポチルに関わることになるその少し前、私は開業臨床心理士として自分のオフィスを開き、サイコセラピーを提供するようになりました。それ以前は精神科医療、あるいは学生相談やスクールカウンセラーとして、無償でサイコセラピーを提供出来る環境に身を置いていたんです。その時には母子家庭であるとか、生活保護家庭であるとか、年金生活者であるとか、非常に貧困の中で生活し、なおかつ自分の心を見つめたい。自分の心を何とか癒していきたいという人たちの支援ができていました。
ところが開業してお金をいただいて、有料でサイコセラピーをすると、私がどこかの組織に勤務していたときに提供できていたセラピーを生活が困窮している家庭の人たちに提供できなくなるというジレンマを抱いていました。
なんとかそういう人たちにサイコセラピーを届けることができないだろうかとずっと考えていたんですが、いいアイデアが浮かんでこなかったときに、このサポチルを設立した現理事長である平井さんからサポチルの基礎となる計画を聞きました。「英国では無償で週三回、サイコセラピーが誰でも受けられる。そういうことができる組織、NPOを作りたいんだ」っていう話を聞いて。その理念や考え方に強い共感を覚えて、参加しようというふうに決意したんです。
とても興味深いお話を聞いている途中になりますが、前編はここまでとなります!後編では、鈴木さんがサポチルへコミットメントすることになった重要なケースのお話に迫りたいと思います。
更に深層へ踏み込む後編はこちらから!是非チェックいただければ幸いです!
https://forms.gle/xZSpdmfYvvpxeUyXA
↑ ↑ ↑記事へのご意見・ご感想はこちらから↑ ↑ ↑
__________________________________________________________________________________
【サポチルの今後の展望について】
日本での子どもと家族の支援は、既に一定の公的な支援が行われています。最近では、子ども家庭庁が設立され、全国の地方自治体に子ども家庭センターが設置され、子どもと家族の支援が進められています。しかし、じっくりと子どもや家族を見つめて支援する姿勢が十分に浸透しているとは言い難いのが現状です。精神分析的アプローチのように、非常に細やかな対応をすることは、現代の日本社会の文化や風土において難しい部分もあるのかもしれません。しかしそうしたアプローチで初めて、いわば救われる子どもや家族がいるのではないかと思います。そのため、公的な支援の枠組みには乗りにくい子どもや家族の支援を引き受けることが私たちサポチルの使命だと考えています。
サポチルは、家庭の経済状況にかかわらず、それぞれが抱えている問題に対して支援を行うことで、子どもたちが健全に成長できる社会を目指しています。サポチルでは、現在子どもたちの支援活動を財政面で支えてくださる方を募集しています。
5000円の寄付で、誰かのワンセッションが無料になります。
__________________________________________________________________________________
インタビュー/構成・米澤宙/畑山由華