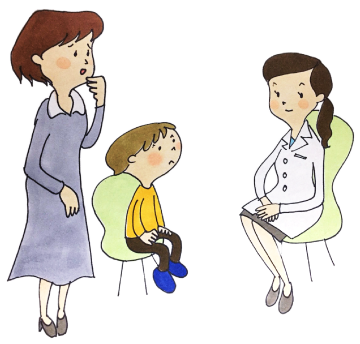コラム
COLUMNちょっとした知識や情報をお伝えするコンテンツ
サポチル20周年記念インタビュー 鈴木誠(監事)「『幸せに生きてもいいんだよ』を見つけるために必要な場所」[後編]
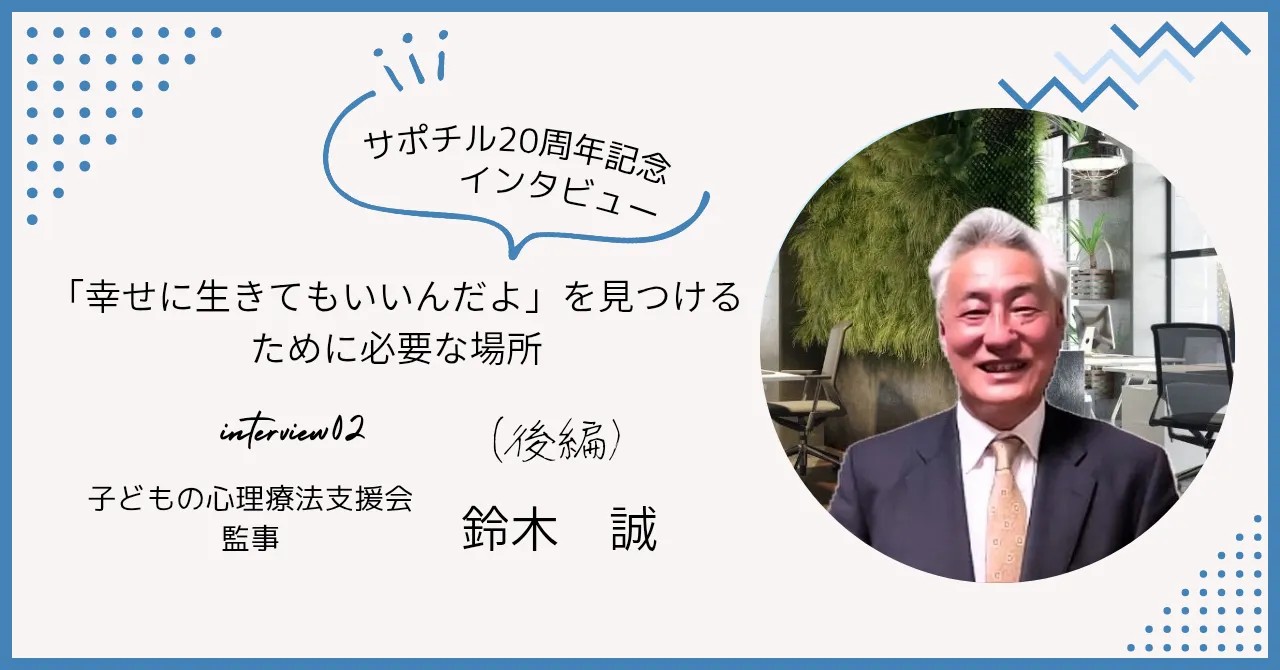
今回お話を伺ったのは、認定NPO法人「子どもの心理療法支援会」(サポチル)の監事を務める鈴木誠さん。
臨床心理士の資格を持ち、三重県にある「くわな心理相談室」では、大人の心理相談のほか、企業や組織へのコンサルテーションを行っています。現在は「日本ワークディスカッション研究会」の理事長としてもご活躍されています。
自身の臨床経験において、支援を必要としているのに費用の関係でそれがか叶わない人たちへ支援を届けたいという葛藤を覚えていたなか、国民が無料で医療を受けられる英国の取り組みをNPOレベルで挑戦するというサポチルの理念へ強い共感を覚え、創設期から活動へ携わってきました。
全2回に渡るインタビュー。前編では、鈴木さんから見る心理療法の現状に切り込む形で、あらゆる現場で子どもの痛みに目をむけにくくなっていることについて詳しくお話を聞かせていただきました。後編となる今回は、鈴木さんがサポチルに携わりながら思い出された印象的なケースについて聞くことができました。
夢物語を実現するために
ー前回は、学校現場では支援を必要としている児童や保護者が存在しセラピーができる心理療法士がいるにも関わらず、組織的な制約によって十分な支援が行われづらいと言うお話でした。社会は子どもの痛みに目を向けにくいということでしたが、現代ではSNS等で世間の声が可視化されやすくなっているようにも思えます。これについてはどう思われますか?
鈴木 そうですね…子どもの痛みが目に見えないものになっていて、可視化できないものはないものとして扱われてしまっているところはありますよね。そういう意味では、我々が取り扱っている「心」というのはそもそも目に見えないもので、それを見えるようにするために精神医学の診断概念を使ってラベルを貼る。例えば発達障害というラベルを貼ると、やっとそこに問題があるんだと目を向けることができるけど、そこにあるのは診断名であって一人一人の子どもの痛みではないんですよ。
あと心理療法そのものがそうかもしれませんけど、体験しないとその良さがわからないという難しさもあると思います。体験して初めて「ああ心と向き合ってもらうっていうのはこんな体験なんだ」となるような、その意義が分かりにくいというところが大きな難しさの一つなんだろうなと思います。
河合隼雄先生が心理臨床の中でよくも悪しくもリーダーであった時には、彼は「物語る」ということを通じて、社会からの「心」に対する関心をぐっと集めていました。そのように虐待によって傷ついた子どもたちの心に社会が目を向けられるような物語を、私たちは作っていく必要があるのかもしれないなというふうに思います。でも、そうするとあまりにも陳腐なものになってしまうので、一臨床家としてはものすごい抵抗があるんですけど。
ー子どもの痛みも心理療法の必要性もなかなか理解されず、ご自身も歯がゆい思いをされたという経験も前半のお話の中には含まれていましたが、鈴木さんの中で、この経験があったから今の考えに繋がっているなと思うことはありますか?
鈴木 率直に言って、20数年前に平井さんと初めて会った時には、私は臨床家としてほとんど児童虐待には関心がありませんでした。むしろボーダーラインや統合失調症などの精神科の疾患の方々に対するサイコセラピーに私の関心は向いていました。
サポチルに関与して十年ぐらいしたときに、友人から『なんでそんな大変なことをやってるの?』と言われて。
当時の私としては当たり前のように感じていたので、『虐待を受けて悲惨な体験を重ねた子たちがいて、なんとかしてやりたいんだよ。』と話したんですが『なんでお前がやるの?お前のもともとの興味は精神疾患を持つ人たちだったんじゃないの?』と言われたんです。
なんでだろうと思ってずっと考えてたら。ふとある時思い出したことがあって。それはサポチルが始まる前に、私が乳児観察セミナーのために平井さんのところに通ってたときに見ていたケースでした。
ーそのケースについて詳しく聞かせてもらうことは出来ますか?
鈴木 大丈夫です※。 その人は当時40代ぐらいの女性で、中学生になった自分の娘に激しい嫌悪感と怒りを覚えて、娘との関係がものすごくギクシャクして。娘が不登校になってしまったので、紹介で私のところに来ることになったんです。
彼女とのセラピーを開始すると、彼女は幼少期に両親が次々と亡くなって、児童養護施設で育った人だということが生育歴を聞いたときに出てきました。そして、施設の中でいじめられたりとか、施設の職員から殴られたりだとか。その一番つらかった時期に、娘が一番幸せそうになっていることに、嫌悪感を抱き始めてしまった。
母親が病気になり、彼女は施設に引き取られたのですが、彼女は自分がお見舞いに行った母親の病床で、『時間だから帰りなさい』とお母さんに言われて。『そんなこと言うお母さんなんか死んじゃえ』と言いながら施設の職員に病床から引き離されて。その晩、自分の母親が亡くなるという体験をしていました。彼女の心の中でずっと自分が母親を殺した、と思いつつ、ずっとその施設の中で耐え、結婚して失敗し、再婚し、そして娘の問題で来談したっていう経緯があったんですね。私はそれまで、これほど深い剥奪を体験した女性のサイコセラピーはあまり体験したことがなかったんです。そんな中、面接場面では彼女のトラウマティックな体験がありありと再現され、私は再現されたものを臨床家として体験しました。
何年か経過して、その方が娘との関係性に改善が見られて、自分自身がいかに傷つきながら生きてきたかということに向き合えるようになって、セラピーが終結するということになりました。
その時に…そのセラピーは毎週火曜日の午前中にやってたのかな?セラピーが終わった時に、彼女は感謝の言葉を、『ありがとうございました。』と私に言うんだけど、私としても彼女からものすごい色々なことを学んだので、『いや、こちらこそありがとうございました』と言って別れることになったんですね。その際彼女は『これで毎週見逃していたスーパーの火曜特売に行けるようになりました。』と話していました。
それと同時に、『自分が施設にいたときにこういうセラピーを受けたかった。今私は先生に救われたけど、今、施設にいる子たちはどうなんだろう。』と言われて。その当時はまだまだ施設に心理療法士が配置されてない時だったので、『まだ無理だと思う。』『どうしたらできると思いますか?』『そうね。宝くじでも当たって見ないと無理かもしれないね。』『じゃあ私も宝くじ買って当たったら、そういう事業があれば、そういうことを先生がもしやるんだったらお金出したい』って。そういう話をして別れました。
あの時のクライアントとのセラピー体験が私の無意識の中でこのサポチルの活動に向かわせていたんだと思います。そしてただ向かわせていただけではなく持続的に、この20年サポチルの事業に積極的にコミットしていこうというふうに私を突き動かしてくれていたんだろうな、と。もちろんこれからも続けていくとは思いますが(笑)
振り返ってみると…サポチルに関わってから十年後ぐらいのある時にそう思ったんです。
彼女が言うように、大人になり成長してから直面した苦悩への克服ではなくて、彼女自身が施設にいた時のような状況へサイコセラピーを届ける…あるいはサイコセラピーが届けられるような社会にしていくことが、このサポチルのミッションなのだろう、そういうふうに思っています。多分この体験がなかったら、ここまで長く続けて来なかったのではないかな。
ーありがとうございます。当時は施設にいる子どもたちに十分なケアがなされておらず、宝くじが当たるほどの奇跡が起きなければ支援につながることもできなかった。支援者としての悔しさ、子どもたちの苦しさをありありと想像できるからこそ、鈴木さんがサポチルを通じて支援の輪を広げていこうとされているんですね。
鈴木 そうだと思います、本当に。無意識のうちにですよね。十年間気がつかなかったのが不思議なぐらいですよ。彼女とのセラピーや体験を思い起こすと、もっと心理療法支援事業を推進するようななりふり構わないパワーがあってほしいなというふうに思います。
子どもの頃に受けたサイコセラピーによって立ち直った、あるいは…ある程度傷にコーティングができて、自分の人生を幸せを求めて生きててもいいんだというふうに思いながら生きていけるようになる。この体験をした人たちはほんと強いですよ。
ー幸せになって生きてもいいんだという場所を与える、社会の場に設けるということもやはり重要ですよね。
鈴木 そういう場があったとして、虐待トラウマを受けた子たちは自己破壊的な生き方、刹那的な生き方しかできないんですよね。だからその場を使うことができない。そしておそらくサイコセラピーは、それを使えるようになるところまでしかできないと思うんです。
サイコセラピーができるのは上から降りてきているクモの糸をつかめるようにするところまでで、そこから先は社会がなんとかしなきゃいけない。
虐待を受けた多くの子どもたちが大人になって成長し、降りてきたいろんな支援のクモの糸を見ることも掴むこともできずにいる。
社会にとって、虐待を受けた子どもたちは見えないものとなっていて、その見えない子どもたちもまた、目の前にあるたくさんの支援が見えない。この双方が互いに視界へ映らないという状況を改善していくことが、サポチルがNPOとして行っていくべき役割だと思います。
救いの手が見えない子どもたちへ『君たちにはまだ見えないかもしれないけど、目を開けると目の前に救いの救命ボートがあるかもしれないし、クモの糸みたいに頼りないものかもしれないけど、救いの綱はあるかもしれないよ』ということを伝える作業ももちろん大事だし、『社会には見えていないかもしれないけど、こういう子どもたちが実際に存在しているんです』という事実を広めていく作業も必要になりますよね。
全部セラピーでなんとかできるわけじゃないですから。
ー社会とのつながり方というか、場をしっかり開拓していくということの意識が必要となりますよね。時代と共に注目が集まっていく心理療法という分野のなか、宝くじのお話も含めてこれからのサポチルの夢そのものを語っていただいたんだなという風に思います。本当にありがとうございました!
※本記事内で語られた事例は、掲載について個人の了承を得ています。また過去に論文としても出版されており、それに伴って内容が一部改変されているものを抜粋・再構成し掲載されています。
https://forms.gle/xZSpdmfYvvpxeUyXA
↑ ↑ ↑記事へのご意見・ご感想はこちらから↑ ↑ ↑
__________________________________________________________________________________
【サポチルの今後の展望について】
日本での子どもと家族の支援は、既に一定の公的な支援が行われています。最近では、子ども家庭庁が設立され、全国の地方自治体に子ども家庭センターが設置され、子どもと家族の支援が進められています。しかし、じっくりと子どもや家族を見つめて支援する姿勢が十分に浸透しているとは言い難いのが現状です。精神分析的アプローチのように、非常に細やかな対応をすることは、現代の日本社会の文化や風土において難しい部分もあるのかもしれません。しかしそうしたアプローチで初めて、いわば救われる子どもや家族がいるのではないかと思います。そのため、公的な支援の枠組みには乗りにくい子どもや家族の支援を引き受けることが私たちサポチルの使命だと考えています。
サポチルは、家庭の経済状況にかかわらず、それぞれが抱えている問題に対して支援を行うことで、子どもたちが健全に成長できる社会を目指しています。サポチルでは、現在子どもたちの支援活動を財政面で支えてくださる方を募集しています。
5000円の寄付で、誰かのワンセッションが無料になります。
__________________________________________________________________________________
インタビュー/構成・米澤宙/畑山由華